こんにちは、みなさん!今日は多くの方が気になっているけれど、なかなか詳しく知る機会がない「ひとり親家庭への支援制度」について徹底解説していきます。
シングルマザーやシングルファーザーとして奮闘している皆さんに役立つ情報をたっぷりお届けしますね!
ひとり親家庭の現状って?
日本では、ひとり親家庭の数が年々増加傾向にあります。厚生労働省の全国ひとり親世帯等調査によると、母子世帯は約123万世帯、父子世帯は約18万世帯と言われています。離婚や死別などさまざまな理由でひとり親になった方々が、仕事と育児の両立に奮闘する姿は本当に尊いものです。
でも実際のところ、経済面での苦労は大きいですよね。特に母子家庭の平均年間収入は、一般世帯の半分以下という統計もあります。そんな厳しい状況を少しでも改善するために、国や自治体はさまざまな支援制度を用意しているんです。
「でも、どんな支援があるのかわからない…」という声をよく聞きます。確かに情報が散らばっていて、自分が受けられる支援を把握するのは大変。今日はそんな支援制度を分かりやすくまとめていきますね!
ひとり親家庭はどんな支援を受けられる?

ひとり親家庭が受けられる支援は実はたくさんあります!主な支援制度を見ていきましょう。
1. 児童扶養手当
まず最初に知っておきたいのが「児童扶養手当」です。これはひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるための手当で、18歳に達した後の最初の3月31日まで(障害がある場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。
金額は、2024年度の場合:
- 児童1人の場合:月額43,070円(全部支給)~10,160円(一部支給)
- 2人目:月額10,170円(全部支給)~5,090円(一部支給)を加算
- 3人目以降:1人につき月額6,100円(全部支給)~3,050円(一部支給)を加算
ただし、所得制限があるので注意が必要です。例えば、児童1人を養育している場合の全部支給の所得制限は、年間収入で160万円未満(給与所得者の場合)となっています。詳しくは住んでいる自治体の窓口で確認してみてくださいね。
2. 児童手当
児童手当は、ひとり親家庭に限らず中学校卒業(15歳に達した後の最初の3月31日)までの子どもを育てている方に支給されます。金額は:
- 0~3歳未満:月額15,000円
- 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:月額10,000円
こちらも所得制限があり、制限を超えると特例給付として月額5,000円が支給されます。
3. 医療費助成
多くの自治体では、ひとり親家庭の親と子どもに対して医療費の自己負担分を助成する制度を設けています。これは「ひとり親家庭等医療費助成制度」などと呼ばれ、自治体によって対象年齢や所得制限などの条件が異なります。
例えば、東京都の場合、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童とその親が対象で、医療機関での自己負担分が助成されます。都内で医療を受ける場合は、医療証を提示すれば窓口での支払いが不要になることが多いです。
4. 教育関連の支援
子どもの教育費も大きな負担になりますよね。そんな時に役立つのが以下の制度です:
就学援助制度
公立小中学校の給食費、学用品費、修学旅行費などを援助する制度です。申請は学校や教育委員会を通じて行います。
高等学校等就学支援金
高校生の授業料を支援する制度で、年収約910万円未満の世帯が対象です。公立高校ならほぼ無料、私立高校でも一定額が支給されます。
高校生等奨学給付金
授業料以外の教育費を支援する制度で、生活保護世帯や住民税非課税世帯が対象です。返済不要の給付型です。
奨学金制度
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、自治体独自の奨学金制度があります。特にひとり親家庭を対象とした優遇措置があることも多いです。
シングルマザーになると無料になるものは?

「シングルマザーになると何が無料になるの?」という質問をよく受けます。完全に「無料」になるものと、「大幅に負担が減る」ものを合わせてご紹介しますね!
1. 保育料の減免・無償化
多くの自治体では、ひとり親家庭に対して保育料を減免する制度があります。市区町村によって異なりますが、所得に応じて無料になることもあります。
また、2019年10月から始まった「幼児教育・保育の無償化」により、3~5歳児の保育料は原則無料になっています。0~2歳児も住民税非課税世帯であれば無料です。ひとり親家庭は所得が低い場合が多いので、この恩恵を受けられる可能性が高いですね。
2. 公営住宅の優先入居
都道府県や市区町村が運営する公営住宅(都営住宅、市営住宅など)では、ひとり親家庭に対して優先入居枠を設けていることが多いです。家賃も収入に応じて決まるため、負担が軽減されます。
完全に無料にはなりませんが、民間の賃貸住宅と比べるとかなり安く住むことができるでしょう。
3. JR通勤定期券の割引
JRでは「母子家庭等援護定期乗車券制度」があり、児童扶養手当を受給している方とその子どもが通勤・通学に使うJR定期券が3割引になります。完全無料ではありませんが、大きな節約になりますね。
4. 水道料金・下水道料金の減免
自治体によっては、ひとり親家庭に対して水道料金や下水道料金を減免する制度を設けているところもあります。例えば、基本料金が無料になったり、一定の使用量までは無料になったりすることがあります。
5. 公共施設の利用料免除
多くの自治体では、児童館、公民館、プール、図書館などの公共施設の利用料が減免または無料になる制度があります。子どもの遊び場や学習の場としても活用できますね。
6. 法律相談の無料サービス
離婚や養育費の問題など、法律の専門家に相談したいことも多いと思います。日本司法支援センター(法テラス)では、収入等が一定基準以下の方に対して無料の法律相談を実施しています。
また、自治体の母子・父子自立支援員による相談や、母子家庭等就業・自立支援センターでの相談も無料で利用できます。
知っておきたい!税金の優遇制度

ひとり親家庭には、税金面での優遇措置もあります。主なものをご紹介しますね。
1. ひとり親控除
2020年の税制改正で新設された「ひとり親控除」は、ひとり親(未婚、離婚、死別など)で、生計を一にする子(年間所得48万円以下)を有する方が対象です。所得税は35万円、住民税は30万円の控除が受けられます。
2. 住民税の非課税措置
所得が一定以下のひとり親家庭は、住民税が非課税になることがあります。これにより、様々な支援制度の対象になりやすくなります。
3. 国民健康保険料の減免
多くの自治体では、所得が低いひとり親家庭に対して国民健康保険料を減免する制度があります。完全に無料になるケースもあるので、住んでいる自治体に問い合わせてみてください。
仕事と子育ての両立を助ける支援

ひとり親家庭の最大の課題は、仕事と子育ての両立ではないでしょうか。そんな時に役立つ支援をいくつか紹介します。
1. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金
就職に有利な資格を取得するための講座を受講した場合、受講料の60%(上限80万円、下限12,000円)が支給されます。例えば、介護職員初任者研修、医療事務、パソコン資格などの取得に活用できます。
2. 高等職業訓練促進給付金
看護師や介護福祉士、保育士など、取得に1年以上の養成機関での修業が必要な資格を取得する場合に、修業期間中の生活費として月額10万円(住民税非課税世帯)または月額70,500円(課税世帯)が最長4年間支給されます。
3. ファミリー・サポート・センター
地域の中で子育ての援助を受けたい人と行いたい人をマッチングするシステムです。ひとり親家庭は利用料が減免されることが多いです。急な残業や子どもの病気の時など、柔軟に対応してもらえるのでとても心強いですよ。
4. 病児・病後児保育
子どもが病気になっても仕事を休めない…そんな時に利用できるのが病児・病後児保育です。ひとり親家庭は利用料が減免されることが多いです。
住まいの支援

安定した住まいの確保も大切ですね。住まいに関する支援をいくつかご紹介します。
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金(住宅資金)
住宅の建設、購入、補修などに必要な資金を低金利で借りることができます。返済期間も長めに設定されているので、負担が少なくなっています。
2. 住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に対して、家賃相当額(上限あり)を一定期間支給する制度です。ひとり親家庭も対象となります。
3. セーフティネット住宅
住宅の確保が難しい方向けに、家賃や入居条件に配慮した「セーフティネット住宅」という制度があります。ひとり親家庭も対象となるので、住まい探しの際に活用してみてください。
離婚後の養育費確保のための支援

残念ながら、日本では養育費の支払い率が低いという問題があります。でも、最近では養育費の確保を支援する制度も増えてきました。
1. 養育費等相談支援センター
養育費に関する電話相談や情報提供を無料で行っています。養育費の取り決め方や、支払いが滞った場合の対応など、専門家に相談できます。
2. 自治体による養育費保証制度
一部の自治体では、養育費の立替や保証料の補助を行う制度を導入しています。例えば東京都では、養育費の保証契約を結ぶ際の初回保証料の全額(上限5万円)を補助する制度があります。
3. 法テラスによる法的支援
養育費の請求に関する法的手続きを取りたい場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用できます。弁護士費用の立替えなどを行ってくれます。
知っておくと得する!自治体独自の支援制度
全国共通の制度のほかに、自治体独自の支援制度もたくさんあります。例えば:
1. ひとり親家庭等医療費助成制度の拡充
自治体によっては、国の制度よりも手厚い医療費助成を行っているところもあります。例えば、子どもの医療費を18歳まで完全無料にしているところや、親の医療費も助成しているところなどです。
2. 学習支援
自治体や民間団体が行う無料の学習支援教室があります。子どもの学習をサポートしてくれるので、教育費の負担軽減になります。
3. 生活支援サービス
食事の提供や、家事・育児のサポートなど、生活全般をサポートするサービスを提供している自治体もあります。例えば、ホームヘルパーの派遣や、食料品の配布などです。
申請のコツと注意点

支援制度を利用するためには、自分から申請する必要があります。以下のポイントを押さえておきましょう:
1. 早めに相談する
離婚が決まったら、できるだけ早く自治体の窓口(子育て支援課や児童福祉課など)に相談しましょう。その方が、スムーズに支援を受けられます。
2. 必要書類を事前に確認
申請には戸籍謄本や所得証明書など、様々な書類が必要です。事前に何が必要か確認しておくと安心です。
3. 情報収集を怠らない
支援制度は年々変わっていきます。定期的に自治体のホームページをチェックしたり、「ひとり親サポートガイド」などの冊子を入手したりして、最新情報をキャッチしましょう。
4. 専門家や支援団体を活用する
ひとり親家庭を支援するNPOや団体も多くあります。そうした団体に相談すると、知らなかった支援制度を教えてもらえることもあります。
まとめ:自分に合った支援を見つけよう
ひとり親家庭への支援は、実はとても充実しています。ただ、残念ながら「知らないと利用できない」という現実もあります。この記事を読んで、少しでも多くの支援制度を知っていただけたら嬉しいです。
あなたの状況や居住地域によって、受けられる支援は異なります。まずは自分の住んでいる自治体の窓口に相談してみてください。また、ひとり親支援を専門とするNPOなどの団体に相談するのも良いでしょう。
ひとり親として子育てをするのは、決して楽なことではありません。でも、活用できる支援はたくさんあります。一人で抱え込まずに、周りの支援を上手に利用しながら、親子で笑顔の日々を過ごせますように!
「この制度、私も申請してみよう!」と思った方は、ぜひ早めに行動してみてくださいね。支援制度を知り、活用することが、あなたと子どもの未来をより良くするための第一歩です。
みなさんの子育てライフがより豊かになりますように、応援しています!
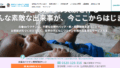
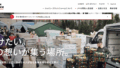
コメント